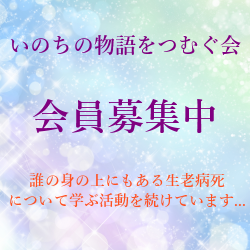井上真由美 看護師
いま、ここに生きている私たちは全て、母の胎内で心臓の拍動を始めました。
「奇跡の一拍目」。
これを起こすために母側から血液の粒を受け取って心臓を完成させることがわかっています。
この命は受け取ることから始まりました。
それは「生きなさい」という愛のギフトだと思います。
受け取った愛をいっぱい育てて、死ぬときに渡して逝けたら。
私自身そのように死を迎えたいし、誰かの死の時が可能な限りそうであるように支えられる医療者でありたいと思っています。
今は「病院で産むことが当たり前」の時代になりました。
それは「病院で死ぬことが当たり前」の時代へと結びつきました。
命の始まりも卒業も、家族の手から離れてしまったことは、この時代を生きる子どもたちの死生観に影響を起こし始めています。
「人はいつか死ぬと思うか?」という質問に「死なない」と答える子どもたちが20%近くもいるのです。
病院で産むこと、死ぬことが「当たり前」となった価値観によって、「どのように産みたいか、どのように死にたいか」という自己決定を希薄させているように思います。
「お任せします」という医療との付き合い方によって、自分や家族の命への尊厳と責任が弱くならないように支えたいものです。
本来、命の始まりと仕舞い方は、家族から学ぶことではないかと思います。
私自身も子どもの頃あんなに若くてなんでもできると見上げていた母と共に生きながら、今、「老いるということ」を見せてもらっています。
いつかあなたもこうなるのだと、それは最後のプレゼント。
*長尾和宏医師著「老いるということ」を朗読させていただきました。
私は14年くらい前に「親は子どもにとって最高のタイミングで死ぬ」という言葉と出会いました。
信じたわけではなかったけれど、ずっと心に残り続け、考えてきた言葉でした。
そんな中、4年前山口県に住む父が肺炎を悪化させ死に向かい始めました。
新潟から仕事を調整しては何度も通って父の看病をしました。

父が息をひきとるときにはそばにいて、声をかけてあげたい、手を握っていてあげたい、体をさすってあげたい、最後の脈を取ってあげたい、ありがとうっていっぱい伝えたいと、あんなにも願っていたのに、父は私の到着を待たずに息を引き取りました。
「自分が本当にやりたいことを選ぶ人生を送りなさい。やりたいことができなかった時の心の痛みを忘れるな。」これは父からの最後のプレゼントだったように思います。
いろいろなことを背負い、本当にやりたいことから外れかけていた自分の人生の軌道修正に勇気が出せました。
もちろん例外はあると思いますが、「親は子どもにとって最高のタイミングで死ぬ」という言葉は、私の死生観の一部になり、私自身が自分の死を思い巡らせる時、大きな安らぎになっています。
更に私ごとですが、21年前に長女を自宅出産しました。
病院出産予定だった私が、それでも私らしいお産の希望を主治医に見てもらうために書いた「バースプラン」がきっかけで、助産師さんとのご縁が繋がり、予定日1ヶ月前に自宅出産が決まりました。
自分が願うお産ができるように、日々の運動や体のケアなど、自分で背負う責任も前向きに取り組むことができました。
ある意味での私のわがままに付き合ってくれた家族たちは、自宅での命の誕生に立ち会うことで、それぞれの人生に大きな成長を果たしていました。
※第3号「つむぐニューズレター」(新潟いのちの物語をつむぐ会)発行2019年(令和元年)5月1日(水)より抜粋
本内容はPDF版より、全12ページすべてを読むことができます(こちらをクリックしてください)